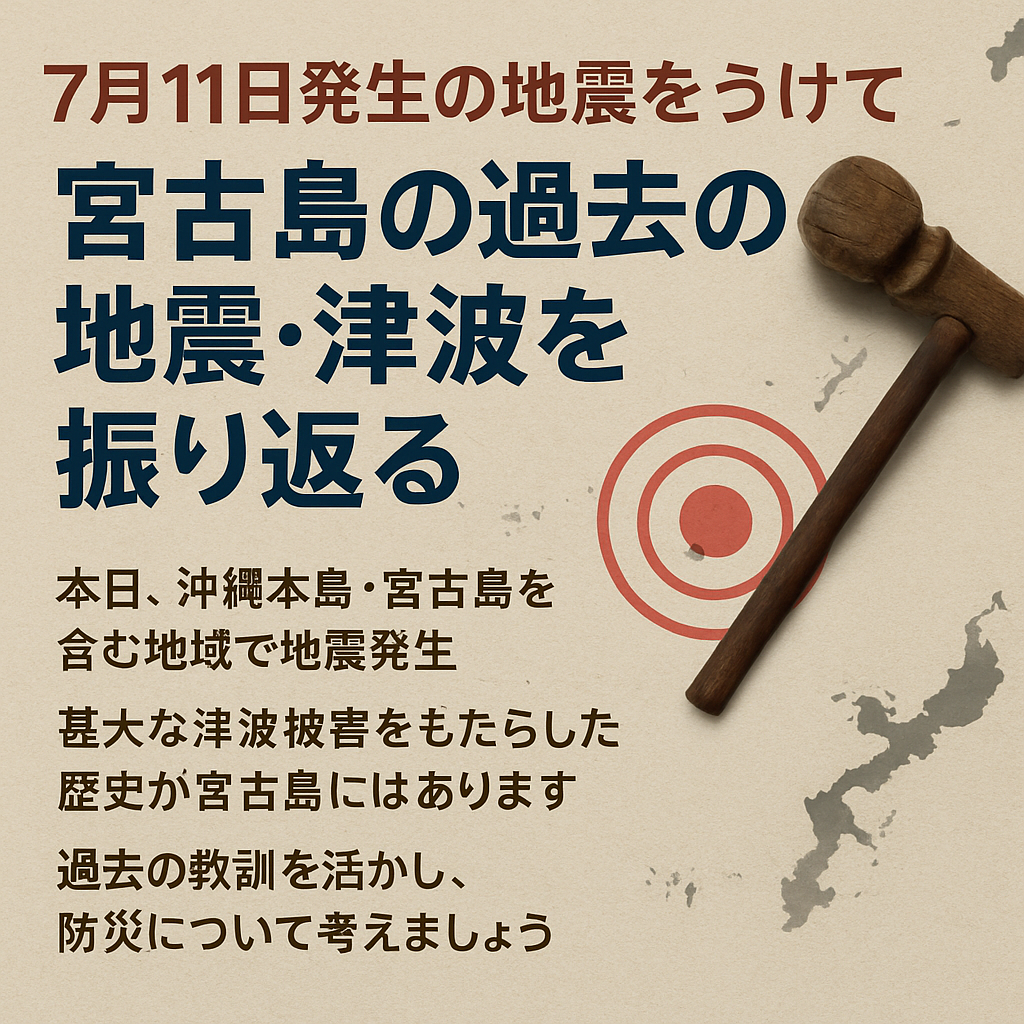
📰【注目】地震を受けて考える|宮古島の過去の地震と津波の歴史を振り返る
宮古島が経験してきた地震・津波の歴史と、いま私たちにできること
2025年7月11日、沖縄本島周辺で最大震度1の地震が観測され、宮古島でもわずかに揺れを感じる地域がありました。被害の報告はないものの、突如として訪れる自然の脅威に、「改めて備えの大切さを感じた」という声が上がっています。
「宮古島は地震が少ないから安心」と言われることもありますが、実は津波による甚大な被害を受けた歴史がある地域でもあります。
この記事では、宮古島が過去に経験してきた地震や津波の記録を紐解きながら、私たちにできる防災の備えを考えていきます。
📜 宮古島の地震・津波の歴史を振り返る
■ 1771年「明和の大津波」
―― 島の形すら変えた未曾有の大災害
- 発生日:1771年4月24日(旧暦 明和8年3月10日)
- 地震規模:推定マグニチュード7.4〜8.5(諸説あり)
- 津波の高さ:最大36〜39m(狩俣では標高17mの地点まで到達)
- 犠牲者数:宮古・八重山諸島全体で約12,000人、うち宮古島域では2,548人が犠牲
この地震と津波は、現在の石垣島の南東沖で発生したプレート境界型の「津波地震」と考えられています。通常の地震と異なり、揺れはそれほど強くなくとも、想像を絶する高さの津波が数十分後に襲来したと記録されています。
津波により多くの村が流され、宮古島や周辺の小島(大神島、来間島など)でも甚大な被害が発生しました。現在も島内各地には「津波石」や「津波記念碑」が残り、後世に教訓を伝え続けています。
■ 昭和・平成以降の地震記録と宮古島
近年では大津波級の地震は発生していないものの、中規模の地震や遠方震源からの津波到達は繰り返し観測されています。
● 1966年3月12日
- 地震規模:M7.5(宮古島近海)
- 概要:小規模な津波を観測。被害は軽微。
● 1998年5月4日
- 地震規模:M7.7(石垣島南部近海)
- 宮古島での揺れ:震度3
- 津波:高さ10〜40cmが各地で観測
● 2010年2月27日
- 地震規模:M7.2(沖縄本島近海)
- 宮古島での津波:最大10cm。揺れは小さいながらも津波注意報が発令。
● 2006年以降
- 年間を通して震度1〜4クラスの小規模地震が数十回以上観測されており、
特に2006〜2010年ごろは活動が活発な時期もありました。
🌊 明和の大津波から学ぶ、災害の本質
明和の大津波が残した最大の教訓は、「揺れが小さくても、津波は来ることがある」という事実です。
現代においても、スマートフォンやテレビから得られる情報を待っていたら間に合わない可能性もあります。
そのため、観光客・地元住民を問わず、地震を感じたらすぐに高台へ避難するという意識を持つことが何より重要です。
🔸 宮古島での防災ポイント
- 津波避難経路の事前確認
→ 滞在先やビーチ近辺の避難所・高台を把握 - 緊急持ち出し袋の備え
→ 水・食料・懐中電灯・モバイルバッテリー・薬など - 警報アプリの活用
→ 気象庁、Yahoo!防災速報、LINE防災などで即座に通知を受け取れる設定を - 観光施設・宿泊施設の掲示確認
→ 避難場所マップや誘導掲示をチェック
🧳 観光客の方へのお願い
宮古島での滞在中、まさか地震や津波に遭遇するとは思わないかもしれません。
しかし、災害は“いつどこで起こるかわからない”もの。だからこそ、最低限の備えと知識を持っているだけで、いざという時の行動が変わります。
「高台はどこか」「逃げるならどの道か」を旅のチェックリストに加えてください。
✅ まとめ:過去を知ることで、未来を守る
今回の地震は被害がないものでしたが、それはたまたま“揺れが小さかった”だけかもしれません。
宮古島は、かつて島の形すら変えてしまうほどの津波に襲われた経験があります。
島に暮らす人、島を訪れる人すべてが、その歴史を知り、「その時」に備えておくことが求められています。
過去の記録に学び、災害への意識を少しずつ日常の中へ。
「備えあれば憂いなし」――それは、観光の安心と命の安全の両方を守るための基本です。
🎯 あわせて読みたい関連記事
- 🌊 明和の大津波|宮古島に残る津波岩の記憶
1771年の大津波が残した巨大津波岩と、その被害の歴史を紹介。 - 🏖 宮古島ビーチで水難事故に注意!
津波や高波時に注意すべき安全行動や避難方法を解説。 - ⚠ 宮古島の海を安全に楽しむ方法
地震や津波のリスクを含めた、海辺での安全対策をチェック。
編集者より:
当サイト「みゃーくずみ」は、 Yahoo!ニュースはこちら をはじめ、下記のメディアに掲載されました。
ORICON NEWS・時事ドットコム・NewsPicks・琉球新報デジタル・沖縄タイムス+プラス・現代ビジネス・ライブドアニュース・ニフティニュース・@DIME・ニコニコニュース・BEST TiMES・ウレぴあ総研・エキサイトニュース・Infoseekニュース・JBpress・宮崎日日新聞 Miyanichi e-press・マピオンニュース・STRAIGHT PRESS・ジョルダンニュース!・PRESIDENT Online・旬刊旅行新聞・antenna ほか多数








最近のコメント